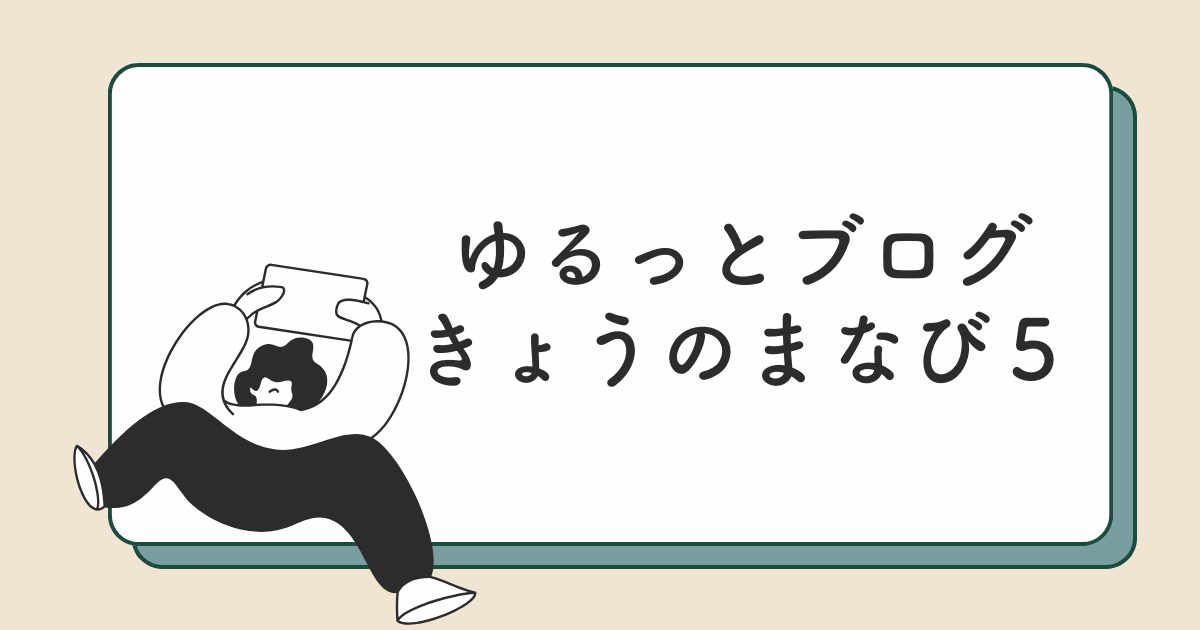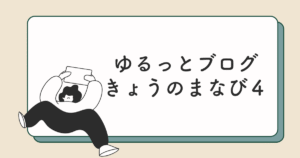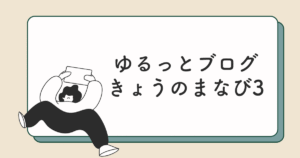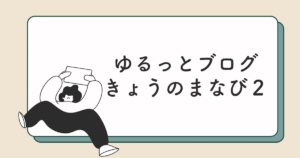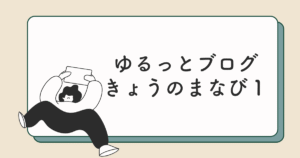今日は、カタ・ウパニシャッドに説かれる「人間馬車説」の復習をしました!
かなりマニアックな内容
でもヨーガの基礎中の超基礎な内容です
頭を整理させるために記録・・・
西暦前3000年頃から伝わるヨーガ聖典「古ウパニシャッド聖典」の教えで、カタ・ウパニシャッドにも人間の構造論が記されています。
古代の人々がこのような人間構造を考え出した理由は、常に動き続けて止まることのない人間という存在を、どのように操縦すればよいのかを探求した結果といわれています。
どんなものも基本構造がわからないと操作できないからです。
5000年間にわたって伝えられてきた「人間五蔵説」と「人間馬車説」は、人間の構造論と機能論を実証的に示すものといわれています。
この「人間馬車説」は、ナチケータス王子と冥界の死神ヤマの物語を通して説かれています。
ナチケータス王子は父ヴァージャシュラヴァサ王を怒らせてしまい、その結果、死神ヤマのもとへ送られてしまいました。
三日三晩、ヤマの帰りを待ち続けたナチケータスは、その誠実さを認められ、ヤマから「どんな願いでも3つ叶えてあげよう」と言われます。
王子の1つ目の願いは「父との和解」、2つ目は「護摩供養を通じて天国へ行くこと」、そして3つ目は「天国や地獄を超えた絶対の世界へ至る智慧の伝授」でした。
しかし、死神ヤマは3つ目の願いだけは叶えたくないと告げます。
なぜなら、その智慧こそが歴代のヨーガ導師たちが伝えてきた「絶対者ブラフマン」を悟るための智慧であり、それを悟った者は死神ヤマの支配を超えてしまう、つまり“死”そのものを超越してしまうからです。
絶対の真智を教える代わりにヤマは金銀財宝や長寿や子孫の繁栄をあげるというが、ナチケータスはそれらの有限なるのもを一切拒否します。
死神ヤマの誘惑にものらないナチケータス。
ここでヤマは人間馬車説を説いていくという物語。
私たちは日々、感覚器官を通してさまざまな刺激に触れています。
しかし、その対象を追い求めてばかりいると、いつの間にか享楽の中に巻き込まれ、生活習慣病や心身症、精神的な不調に苦しむことが多くなります。
現代のストレス社会では、感覚器官を満足させることが生きがいになっている人も少なくありません。
「カタ・ウパニシャッド」では、これを“10頭の馬である感覚器官を制御できず、暴れ馬にまたがって生きているような状態”としてたとえています。
けれども、私たちの内なる心理器官の一つである理智(ブッディ)が智慧で満たされ、物事の真実を正しく認知し、判断し、決断できるようになれば、
外界の事物に過剰適応して暴れ続ける10頭の馬(感覚器官)は、良馬のごとく落ち着いた動きを見せるようになります。
その結果、ストレスの多い日々の中でも、嗜好品や快楽的刺激に過度に依存しなくなるのです。
暴れ馬のような感覚器官を制御できないまま長年過ごすと、その心理作用は中枢神経系だけでなく、内分泌系や免疫系の機能にも影響を及ぼし、肉体のさまざまな臓器をも蝕んでいきます。
しかし、馬車の御者である理智(ブッディ)をしっかりと訓練することで、手綱(意思/マナス)の扱いに迷いがなくなり、やがて至上の境地(三昧の境地)が日常の中でも実現されていきます。
その結果、心身の乱れに起因する発病の活性化を予防できるようになるのです。
こうした心身の健やかさを目指すのがヨーガであり、そのための理智の訓練(理智教育)を、肉体(アーサナ)・呼吸(プラーナーヤーマ)・瞑想(ディヤーナ)の三次元で実践していきます。
理智の訓練こそが、ヨーガにおける究極の健康促進法だといわれています。
感覚器官は本来、衣食住や快楽などの対象に引きつけられる性質を持っています。
しかし、その対象に向かう手綱である意思の働きを外界ではなく内側に向けるよう、理智(ブッディ)が巧みに操作できるようになると、たとえ外の世界にどれほど快楽的な事物があっても、私たちの心はそれらに引きつけられなくなります。
つまり、理智が意思よりも優位に働く状態では、意識は内側の核である真我(アートマン)に向かい、
その生命の源の前にひれ伏すような謙虚な心持ちが生まれます。
そしてこの謙虚さの中で、外界への過剰な適応を完全に克服した状態こそ、ヨーガが説く最高の健康状態といえるのです。
ウパニシャッドの教えでは、天国や地獄のような二極の世界を超えた、ナチケータスが求めたような究極の境地に至ることが説かれています。
ヨーガの最終目的もまさにこの絶対の境地(解脱)であり、そこでは生と死、快と苦といった相対の世界を超えて、真の自由と安らぎが得られるといいます。
この絶対の境地に到達するためには、聖典に記されているように「鋭く精妙なる理智を有する観想者」による修行が必要です。
つまり、意識化(マインドフルネス)の力を鋭くし、「変化するもの」と「変化しないもの」を見極める識別の修行を通して、変化しないものを自己存在と合一させる訓練を行うことが求められます。
理智を磨き、心を静めることで、永遠に変わらない自己(アートマン)へとつながる道が開かれていくのです。
カタ・ウパニシャッドで説かれるこの考え方は、インドで古くから親しまれてきた人間構造論と機能論に基づいており、人間そのものをどのように操縦するかを理解する上で欠かせない教えです。
身体や感覚、心、理智、真我といった人間の多層的な構造を理解し、理智を通じてそれらを調和させることが、安定した心身の状態をもたらします。
この古代の智慧は、現代の健康促進にも応用することができます。外的な刺激やストレスに振り回されるのではなく、理智を通じて内面を整えること。
これこそが、心身の健康と安らぎを保ちながら生きるための大切な鍵なのです。
〜人間馬車説の詳細〜
この「人間馬車説」では、人間の構造が10頭立ての馬車としてたとえられています。
その10頭の馬とは、5つの知覚器官(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)と、5つの運動器官(手=授受器官、足=移動器官、生殖器、排泄器官、発語器官)のことを指します。
馬を操る手綱は、馬(感覚器官)と御者(理智)の間で情報をやりとりする心理器官であり、これは「意思(マナス)」と呼ばれます。
そして御者にあたるのが「理智(ブッディ)」で、知性や感性をもとに判断を下す働きを担っています。
さらに、その御者の後ろには2つの心理器官「我執(アハムカーラ)」と「心素(チッタ)」が控えています。
理智が判断を下す際、我執(アハムカーラ)はそこに「自分の」「自分が」という意識を結びつけ、心素(チッタ)は過去の記憶や心理的印象を蓄えておく“倉庫”のような役割を果たしています。
つまり、心素(チッタ)は“記憶袋”のようなものであり、トラウマや潜在意識といったものも、すべてこの心素の中に蓄えられていると考えられています。
ヨーガでは、すでに4000年以上前からこの心理構造が知られていたのです。
カタ・ウパニシャッド第3章3〜4節には、次のように説かれています。
「真我(アートマン)を車中の主人と知れ。身体(シャリーラ)は車輌、理智(ブッディ)は御者、意思(マナス)は手綱と知れ。諸感覚器官は馬たちであり、感覚器官の対象物が道である。真我と感覚器官と意思が一つとなったものを、賢者は享受者(ボークタ)と呼ぶ。」
また、ヨーガ・スートラにも次のように記されています。
「記憶とは、かつて経験した対象を心素(チッタ)の内にとどめることである。」
このように、人間馬車説は心の構造と働きを、驚くほど精緻に表現した古代インドの智慧なのです。
いや〜長いっ
ここまで読んだあなたは
ヨーガの歴史に興味があるのでしょうか!
これを言葉で簡単にわかりやすく伝えるのも難しい!
ここで改めてまとめたことで理解が深まった〜